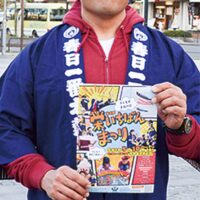健やかなる成長を
七五三は、11月15日の前後に三才(男児・女児)・五才の男児・七才の女児が家族と一緒に御神前で、これまでの無事を感謝し、今後の健やかなる成長を祈願するものです。
七五三の由来
元々は古くからの風習に由来するもので、代表的なものだと、三才の「髪置」、五才の「袴着」、七才の「帯解」です。「髪置」は男女児ともに行われた儀式で、この日を境に髪を伸ばし始めました。また男児は「袴着」で袴を着始め、女児は「帯解」でそれまで付け紐で着ていた着物から帯でしめる着物に替えました。これによって晴れて一人前として認められたのです。七五三参りは昔は数え年で行いましたが、近年では満年齢で行うことが多くなっています。
ご祈祷は土日祝なら当日受付可
10月27日(土)~11月25日(日)までの土曜・日曜・祝日は、事前予約が必要ありません。当日、受付で申込用紙に住所、氏名等を記入し、すぐにお参りできます。御祈祷の開式は9:00~16:30です。
上記以外の平日は電話で予約が必要。開式は9:00~16:00です。※平日は終了時間が30分早まります。
衣装貸出・写真撮影も
専属業者による衣装の貸出と写真撮影を10月20日(土)~11月18日(日)までの土曜・日曜で実施。10月20日・21日は神社内のスタジオのほか、外でも撮影するロケーションフォトを実施。そのほかの土曜・日曜はスタジオ撮影となります。各日程で先着順の受付。詳細、申込みは式典写真協会(TEL 0120-073-753)まで。

1187年創建 歴史とともに歩む神社
文治三年(1187年)五月、武蔵国桝杉城主・稲毛三郎重成により創建された同神社。重成は敬神の念が篤く、所領稲毛に稲荷社を建立すると共に霊的な夢のお告げを受け、日本武尊(ヤマトタケルノミコト)及びその妃、弟橘比売命(オトタチバナヒメノミコト)を御祭神としてこの地に祠を建て、白鳥前川神社と名づけたと言い伝えられています。天正十年(1582年)火災により社殿が焼失し、当時この地を治めていた上杉景虎(謙信の子)が社殿を新しく建立、寄進し、かつ毎年春秋の上納金より三貫文を社料として免租するという内容の古文書も残されています。
以後、現在まで厄除祈願や安産祈願、初宮詣、地鎮祭など、地域との関わりを大切にしてきました。

毎年多くの人が訪れる節分祭(2月)

思い入れのある人形を供養する人形供養祭(4月)

穢れを払い、健康を祈願する夏越の大祓式(6月)