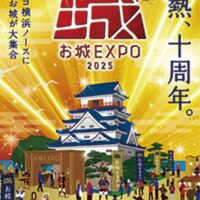2018年に横浜市認定歴史的建造物に認定された「中山恒三郎家」(川和町890)が10月19日(日)、一般公開される。午前10時から午後3時まで。見学は無料。
公開施設は、認定建造物の書院=写真=や店蔵のほか、諸味蔵、麴室、八号蔵。
書院は、明治時代に接客施設として竣工され、2016年に敷地内の整備で現在地に曳家された。当日は内部見学が可能で、邸内で調査・整理中の資料の一部も展示される。
醤油の元となる諸味を保存していた諸味蔵も内部見学可能。民俗資料と市歴史博物館の学芸員の整理作業が公開される。
店蔵は、敷地内で最も古い建物の一つ。中山家の家業だった「中山恒三郎商店」の主に酒の卸売を取り扱っていた建物。醤油の醸造に必要な麹を作っていた煉瓦造りの麴室や八号蔵を含め、外観から往時を偲ぶことができる。
中山恒三郎家は、駐車場がないため、公共交通機関の利用を(市営地下鉄川和町駅出口2から徒歩10分/東急バス・市営バス川和団地下バス停下車徒歩2分)。
菊園としても有名
中山恒三郎家は、江戸時代から川和町で酒類販売のほか荒物雑貨や呉服織物を扱い繁栄。明治時代には醤油醸造、煙草・塩の販売、製糸業なども営み、昭和初期には都築郡一の豪商といわれた。
また菊栽培にも力を注ぎ、明治末期には1500種の菊を栽培したと伝えられる。自宅に菊園「松林圃」を作り、観菊会を開き、皇族や各界の著名人から注目を集めたという。