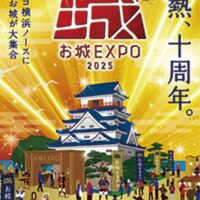海老名町と有馬村が1955年7月20日に合併してから70周年となった。「昭和の大合併」の動きのひとつで、合併促進法の施行から約2年、議論の末に生まれたのが新「海老名町」だった。市歴史資料収蔵館(河原口)には、当時の膨大な事務作業を物語る引継書や新町建設計画などが展示されている。
新町名で難航
戦後、GHQは行財政改革のため「シャウプ勧告」を出して合併を促した。これを受けて国は53年に町村合併促進法を制定。県は鵜飼信成東大教授による合併試案を示し、高座郡では10町村の合併案などを示した。
こうした中、人口約1万千人の海老名町と約5千人の有馬村は、農業地帯としての一体性などから合併に向けた協議会を立ち上げた。議論は順風満帆とはいかず、新しい町名をどうするかで難航。有馬村にとっては「有鹿郷」や「恩馬郷」などに由来する、長年親しんだ村名が消える事に抵抗もあった。一時は合併不可能と新聞に報じられるほど混迷したが、最終的に有馬村が「大乗的見地」(大乗=多くの人々を悟りに導き救済するなどの意味)から新町名を受け入れ、合併の合意に至った。
その後協議会で合意した新町建設計画では、小田急線海老名駅の北側に相模線の新駅(国鉄海老名駅)の設置やその結果「極めて理想的な環境になり将来の発展が期される」など今の海老名を描くような提言もあった。
初代町長選では無投票となり、渡辺正吉が当選。その後も厚木市からの合併申し入れや綾瀬町からの合併申し入れ、大和町・綾瀬町・座間町・渋谷村との5町村合併などが浮上したが、海老名町は積極的にならず、71年には市制が施行され、今に至っている。
9月28日(日)まで、同館には当時の写真や分厚い議事録、「茶だんす」や「火鉢」「蚊帳」など当時らしい品目を記した財産目録などが展示されている。月・火曜休館。
(問)海老名市歴史資料収蔵館【電話】046・232・3611