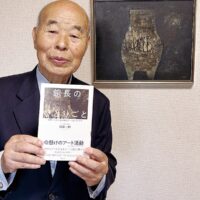「原三溪の美術 伝説の大コレクション」がこのほど、横浜美術館(逢坂恵理子館長)で始まった。主催は同館と日本経済新聞社。同館開館30周年と三溪の生誕150年、没後80年を記念したもので、逢坂館長は「三溪を主題にした企画展は念願だった。様々な側面を持つ彼の姿をお楽しみください」と呼びかける。9月1日まで。
原三溪(1868年〜1939年)は、横浜において生糸貿易や製糸業などで巨大な富を得た実業家。三溪園=中区本牧三之谷=は、三溪がつくり出した最大の作品だ。
30件以上の名品
同展では、文化人である三溪を「コレクター」「茶人」「アーティスト」「パトロン」の4つの側面に焦点を当て、プロローグから第5章まで4つの展示室で展開する。三溪が、大蔵大臣などを務めた井上馨から1万円という当時では破格の値段で買い取ったことで有名な国宝『孔雀明王像』をはじめ、全国から三溪にゆかりある作品を集め、国宝や重要文化財に指定される名品が30件以上あるほか、原家の協力により三溪旧蔵の美術品や茶道具約150件が揃っている(一部展示期間が限定される作品もある)。観覧料(税込)は一般1600円、大学・高校生1200円、中学生600円となる。
自ら漢詩、絵画も
三溪は美濃国(現在の岐阜市)で庄屋を務める青木家の長男として誕生。17歳で上京し東京専門学校(現在の早稲田大学)で政治と法律を学ぶ。23歳のとき、生糸業で財を成した横浜の実業家原善三郎の孫娘である安(やす)と結婚したことで、横浜に拠点を移し、原家の家業を継いだ。
生糸の事業拡大に取り組む傍ら、家業を継いだ3年後には、三溪園内に私邸を建て造園に着手。そこで、美術品の収集や作家の支援、茶を通じた文化人たちと交わりを楽しんだほか、自らも漢詩をよみ、絵画を描いた。
記録をたよりに
各展示室には、三溪が収集した作品のほかに、1893年から1929年までの37年間にわたる美術品の売買実績を記した全5冊の「買入覚」をはじめ、自筆で作品を記録した資料群が収められている。
内山淳子主任学芸員は「展示構成を考えるときに、三溪を読み解く資料として参考になるものでした」と解説する。
展示期間中は、同展の観賞券を提示すると美術館、三溪園が相互割引になる。柏木智雄副館長は「古建築の三溪園と同展の作品を双方に見ることで、三溪の世界を楽しんでほしい」と話す。
問い合わせは横浜美術館【電話】045・221・0300へ。