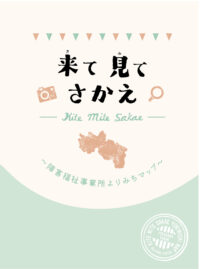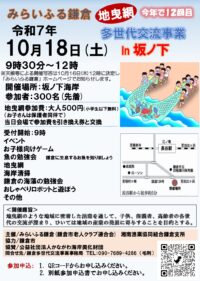川崎地名研究会(菊地恒雄会長)は発足40周年を記念してパネル企画展「川崎の地名―地名を通して、市民と共に―」を2024年1月14日(日)まで、東海道かわさき宿交流館(川崎区)で開催している。午前9時から午後5時まで。入館無料。
2024年市制100年を迎える市の変遷とともに失われてしまった地名や、今も残る由緒ある史跡などを各区から5点選び、写真と資料を掲載したパネルで展示している。
引き継がれる名称も
中原区からは木月堀・井田堀、禁足地、八百八橋、小杉御殿町、井田を紹介。かつて用水掘に架けられていた八百八橋は、江戸時代中期に丸子の渡し場近くに住んでいた野村文左衛門が私財を投じた石橋。現在は区役所の南庭や、武蔵小杉駅北口ロータリーの歩道橋の下に復元されたものが展示されている。
高津区からは溝口、円筒分水、しばられ松、二子塚、橘樹を紹介。中でも「橘樹」に関しては、日本書紀の中に「橘花」という記述があり、今から1400年以上前から、現在の川崎市辺りが「たちばな」と呼ばれていたことをうかがわせている。本来「橘」だけで「たちばな」と読むが、713年の和銅官命により地名は漢字2文字とすることから「橘樹」とされた、としている。

川崎市初の国史跡に指定された「橘樹官衙遺跡群」
宮前区からは、三ツ又の庚申堂、王禅寺道、とんもり谷戸、馬絹古墳、影向寺を紹介している。
多摩区は「雪ケ坂」「大道」「小沢城跡」「枡形城・広福寺」「下綱」を紹介。雪ヶ坂のパネルでは、「北向きの急坂で雪が降ると半日経っても溶けず、その上に雪が降れば通行に難儀な道だった」などといった紹介がされている。
担当者は「無くなった地名も橋や道路などに引き継がれて残るものがある。自分たちの街の歴史を知り、地名の由来と役割を考える機会にしてもらえたら」と話す。