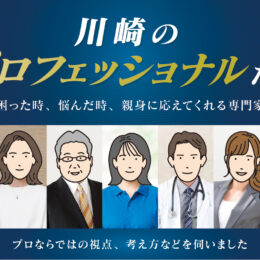神輿の魅力「担げば伝わる」
各地で「お祭り」が開かれるこの時期。それぞれの地域で親しまれてきた「神社のお祭り」も昨今では担い手不足などを抱えていることが珍しくない。そんな中、泉区・須賀神社の神輿文化を守ろうと尽力している一人が会社員の長嶋康太郎さん(42)だ。神輿渡御の当日7月27日(日)には「担ぎ方講座」を開き、広く参加を募っている。
7月26日・27日に例大祭を控える和泉中央南の須賀神社。27日の夕刻には神輿渡御が行われ、同神社の神輿が長後街道にも姿を現す。現存する神輿は1950(昭和25)年に奉納されたもの。「須賀神社の神輿は大きいんですよ」と長嶋さん。総重量は800kgにも及ぶという。
長嶋さんはいずみ野小、中和田中の出身。「祖母の家がいずみ中央のあたりで、毎年お祭りの時には親戚がみんな集まったんです。露店が並んでいて、いとこたちと楽しんだ思い出があります」
世代を越えた一体感
神輿を初めて担いだのは大学生の頃。その時の高揚感は今も色あせない。「非日常というか、いい大人が大きい声を出して盛り上がるのが楽しくて。しかも自分よりずっと年長の人たちもですよ」。世代を越えた一体感が心地よかった。
大学卒業後は仕事の都合で三重県に暮らしたが、毎年お祭りの時期に合わせて泉区に帰省した。激務で心身ともに疲弊していたが、むしろ「神輿を担いで無心になりたかった」と振り返る。
転職を機に生活の拠点を泉区に戻すと、今まで以上に神社に関わるようになっていった。その背景にあったのは少しずつ感じていた危機感だった。
減少する地元の担ぎ手
「昔はもっと『須賀神社』の文字が入った半纏を着ている担ぎ手が多かったんですよ」。今では地元の担ぎ手は一割ほどにまで減っており、区外からの担ぎ手が支えているという。「学校でいえば、文化祭や体育祭がなくなったらさみしいのと同じで。伝統ある神社のお祭りや神輿の文化を、次の世代にも残したいんです」。そんな思いから、頼まれたわけでもなく自ら広報を買って出た。
今年の講座
「痛み軽減のために肩にタオルを」「疲れたら無理せず休んで」――担ぎ方のコツをまとめ、昨年初めて中学生以上を対象に講座を開催。若者が10人ほど参加するなど、手応えはまずまずだ。「実際に担いでもらったら楽しさが伝わるはず。小6の娘も、『(中学生になる)来年は担ぎたい』んですって」と笑顔で明かす。
今年の担ぎ方講座は27日午後4時からリョーコーホーム(株)(泉区和泉中央南3の1の6)で。事前の申込みは不要。