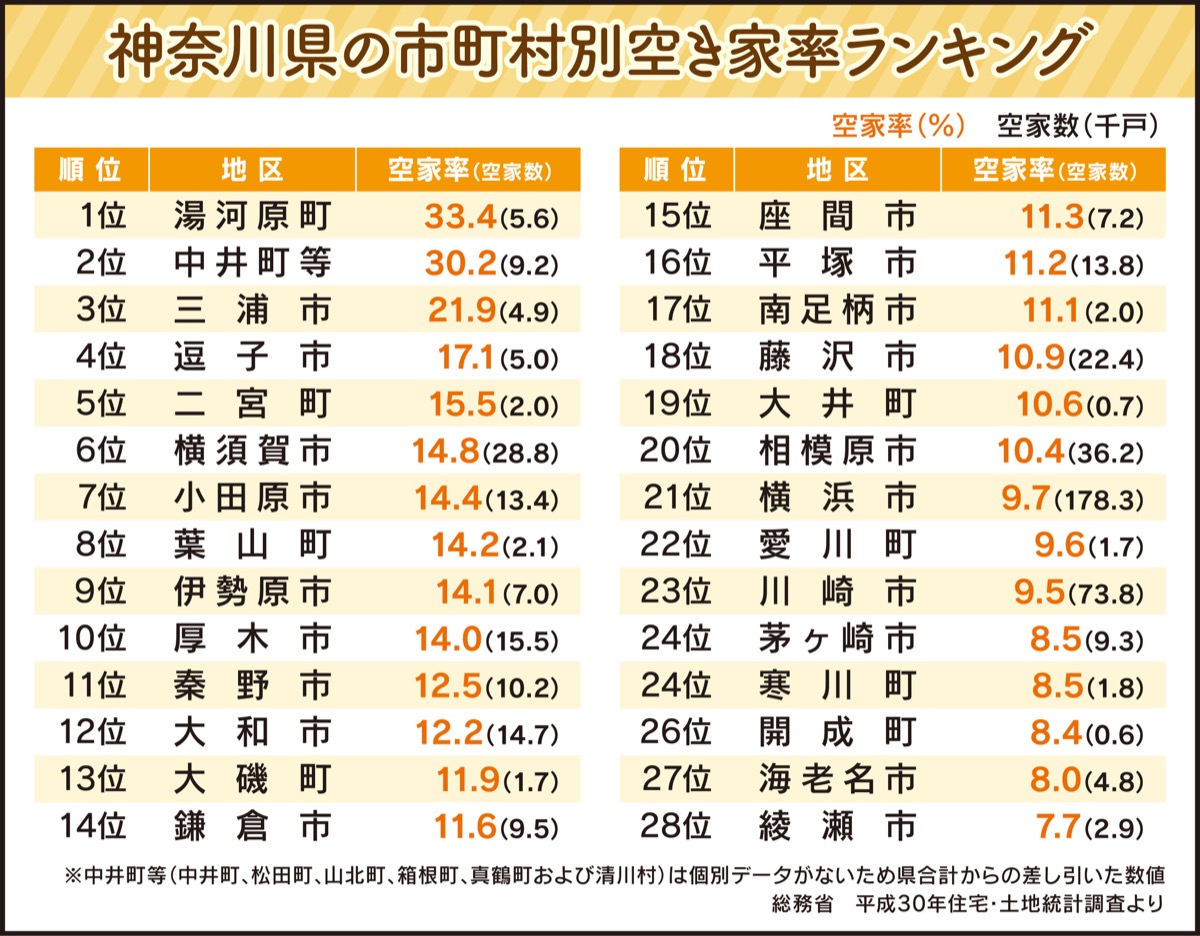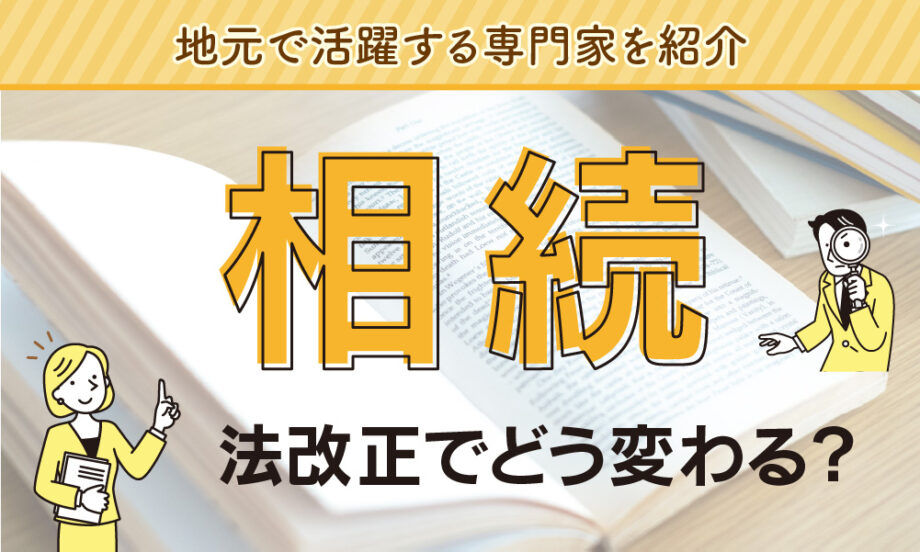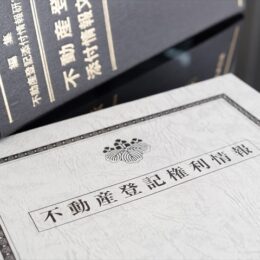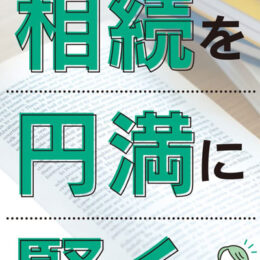誰にでもやってくる相続、とは言え、法律の知識があるわけでもなく、書類もややこしく、誰に相談したら良いか見当もつかない、という方も多いのでは。財産のこと、家・土地のこと、スムーズに引き継げるよう、生前の準備が大切です。まずは主だった相談先から押さえていきましょう。
■最寄りの行政機関(役所や税務署などの無料相談) ■税理士 ■弁護士 ■司法書士 ■行政書士 ■銀行 ■不動産事業者、コンサルタントなど。
スペシャリストの得意分野
それでは、各専門家の特徴を見ていきましょう。
- 税理士:正確な相続税の試算を知りたい場合に。そもそも相続税の申告が必要のないケースもあります。
- 弁護士:遺産分割や遺言書で揉める、もしくはすでに揉めているなど、交渉事が必要な場合。
- 司法書士:不動産の名義を変更(相続の登記)する場合。
- 行政書士:戸籍謄本など必要書類の収集、登記や税務申告以外の代理。
- 銀行:不動産や投資信託、株式など、遺産が多岐にわたる場合。納税資金の相談。
- 不動産事業者、コンサルタント:相続にまつわる資産・土地活用に関する専門知識が豊富。
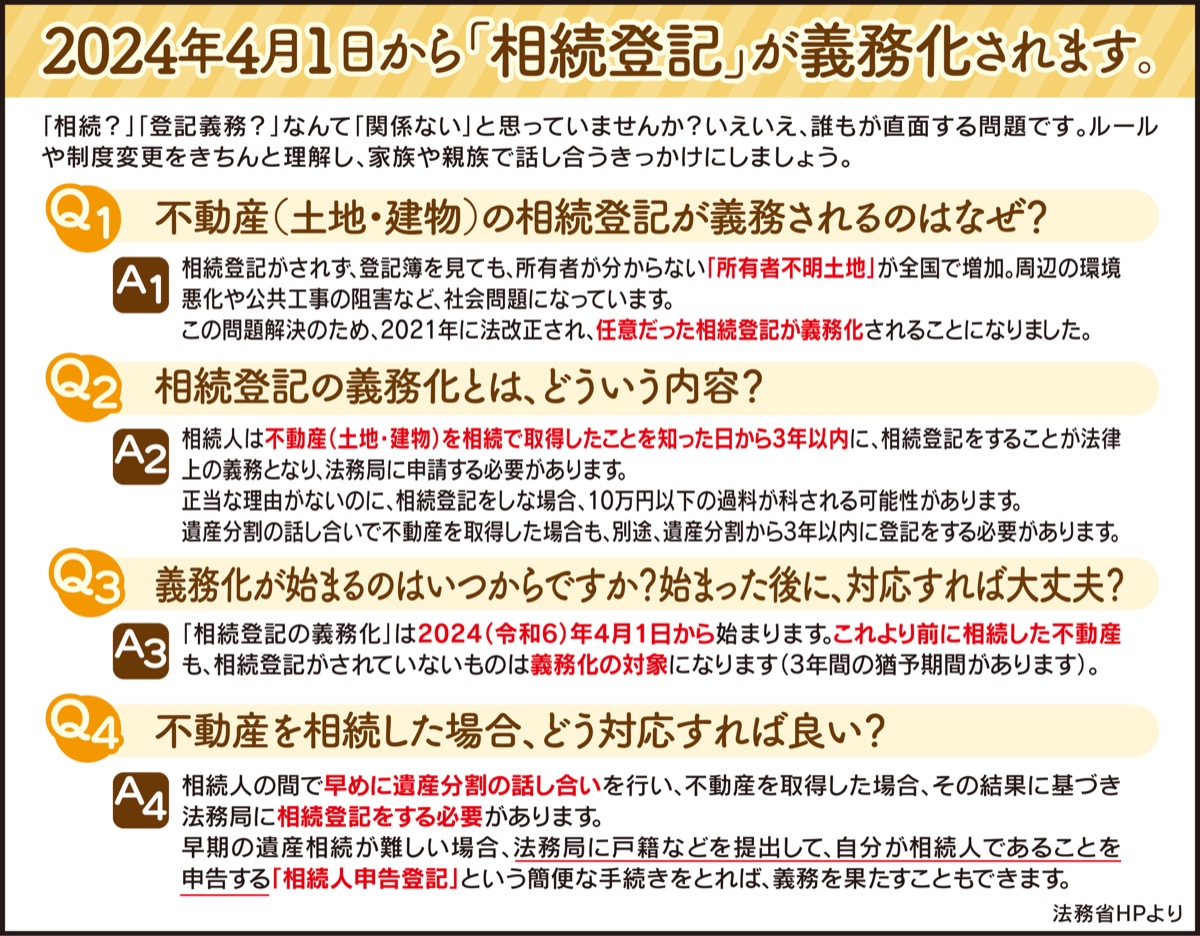

【エリアで選択】
◆横浜の専門家たち
◆川崎の専門家たち
◆相模原の専門家たち
◆湘南地域の専門家たち(平塚・茅ヶ崎・藤沢・鎌倉・大磯・横須賀)
◆県央地域の専門家たち(秦野・厚木・座間・伊勢原・大和・海老名)
◆小田原の専門家たち
◆東京多摩地域の専門家たち(町田・八王子・多摩)