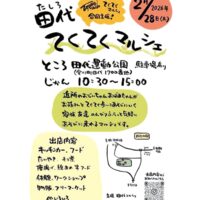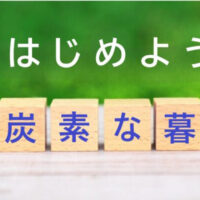コラムの第三弾に登場するのはけやきロード本郷台駅前商店会の「そば処 深山」の4代目店主、南條義和さん。今回は家庭でもできる「お店並みに美味しい天ぷらの作り方」を伝授してもらいました。
南條義和さん
このコラムで地元商店の皆さまの技や知恵をご紹介しながら、商店街の皆さんの人柄も知っていただきたいと思います。ぜひ、皆さんも栄区の商店街を知っていただき、足を運んでみてください!
サクサクの衣は水と油の温度が重要
本郷台駅前に店舗を構える「そば処 深山」は創業から50年以上の老舗。長年地域住民に愛されてきました。4代目店主の南條さんは10年ほど前から深山で働きはじめ、伝統の味を受け継いでいます。
そんな南條さんが天ぷらを作るうえで大切だと語るのは水と油の温度。「温度管理がされている水と油を使用するのが、サクサクの衣にするうえでの重要なポイントです」と教えてくれました。このポイントを踏まえて、実際に天ぷらを作ってもらいました!

氷水に浸した具材
まずは具材の準備から
今回使用する具材は天ぷらの定番であるエビと、夏野菜のナス・ピーマン。それぞれ切り方にも工夫が施されています。
- まずエビは殻を剥ぎ、背ワタなどを取ります。
- エビに切り込みを入れる
- 手で伸ばして真っすぐに
その後は背中が曲がったエビの腹側に切れ込み5か所ほど入れ、千切れない程度に身を反らします。そうすると、エビは真っすぐになり揚げた時に見栄えも良くなります。また、暑い時期などは身が傷みやすいので、揚げる直前まで冷やしておくことをオススメします。
- 次にナスはヘタを包丁で落とした後、縦4分の1にカット。
根本を1㎝ほど残して、3ミリ幅にスライスしていきます。こうすることでナスが扇形になり、見た目も華やかになりました。また、この切り方だと表面積が増え、揚げ時間の短縮にもなります。冷水に軽くさらして灰汁を取れば完璧です。
- 切り込みを入れて扇形に
- 縦に4等分
最後にピーマンはヘタの部分を落として、食べやすいように縦に4等分。その後は水が入っているボウルの中でタネを取っていきます。
「黄金色の衣」を目指して
次に薄力粉200g、卵1個、冷水400㏄の割合で用意します。水に薄力粉と溶き卵を加えて、粉がダマにならないようにかき混ぜましょう。この時、水は冷蔵庫でよく冷やした水、もしくは氷水を使用します。温度が低い水を使うことで、衣が「サクッ」とした仕上がりになります。

溶き卵を流し込む
そして、フライパンに油を2cmほど注ぎます。目安の温度は180℃。170℃を下回ると衣が柔らかく、190℃を越えると衣が焦げやすくなってしまいます。
ではそれぞれの具材に下粉(薄力粉)をまぶし、まんべんなく衣をつけてから油に投入していきます。

美味しい匂いが漂ってきました
揚げる時間は3分が目安。黄金色になったら油をよく切って、盛り付けましょう。

綺麗に揚がった天ぷら
どれもサクサクとした食感でタレとの相性が抜群。また下粉をしているおかげか、途中で衣が剥がれることもなく最後まで美味しくいただきました。

サクサクの天ぷらが温かいご飯とタレとベストマッチ
「1人でも、家族でも!」多様な人が集う街のそば屋

お店は本郷台駅出て、すぐ
そばや天ぷらだけでなく、丼物やおつまみなど多くのメニューを揃えている「そば処 深山」。平日はお得なランチメニューを求めて本郷台駅周辺で働く人々、夜は帰宅前に晩酌をする会社員や家族連れなど、日夜問わず、様々な人が訪れています。「長年通ってくれる常連さんもいて、お客様との距離も近いと思います」と微笑む南條さん。
「一人でも、家族でも。いつでもふらっと来てください。」「本郷台で少し腹ごしらえを、、、」と思ったらぜひ訪れてみては。
今後も商店街の皆さんの温かさと技術を感じていただけるよう、様々な情報を発信していきます。けやきロード本郷台駅前商店会にもぜひ足を運んでみてください。
併せて読みたい