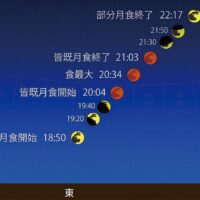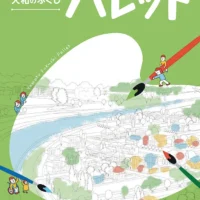三浦半島の特産品である「三浦大根」がブランド化され、2025年で100年を迎えた。命名されて以来、三浦特産の冬大根として名声を維持してきた。しかし栽培が容易で手間が少ない他品種の台頭などにより、いまでは三浦市農協へと共販出荷される約99%が青首大根となっている。その反面、冬の時期には正月用の商材として、また、三浦大根を求めて直売所に足を運ぶ人もいるなど、いまだ根強い人気を誇る。100年の歴史を改めて探った。
50年の天下と50年の堅守
三浦市で生産される大根の歴史は古く、『新編相模国風土記稿』(1841)には、高円坊村(現高円坊)の大根が上品として名を馳せていたと記述されている。ただ、当時の大根は根がねずみの尾に似た「ねずみ大根」と呼ばれる、今の三浦大根とは異なる品種だった。その後、1905年に「三浦郡農会」の鈴木寿一氏により練馬ダイコンの種子が持ち込まれると、高円坊や小原などの大根と交雑が行われるように。そして25年、同会の岸亀蔵氏が「三浦ダイコン」と命名した。
これ以降、ポスターやのぼりなどで宣伝がなされ、ブランド品として確立化が進んだ。しかし79年10月、大型台風が三浦大根を襲う。播種を終えていたこともあり、代用として関西地方を中心に栽培されていた青首大根が投入された。栽培が容易で収量が多い点、作業量減少などが生産者にマッチ。消費者のニーズにも合致した。以降数年の内に青首大根がシェアの大部分を占め、現在に至る。
三浦大根は柔らかな肉質とみずみずしい甘み、煮崩れしづらいといった特徴があり、現在、主に正月商材として年末期に出荷されている。また、冬期には一部直売所でも販売され、足しげく通う根強いファンも存在する。2004年には三浦海岸駅前の飲食店主らでつくる「みうら江戸前倶楽部」が三浦大根を原料にした「だいこん焼酎三浦」を商品化するなど、まちおこしにも活用されてきた。
三浦半島に根を張り100年。長い歴史の中で希少性の高い大根へ変遷してきた。