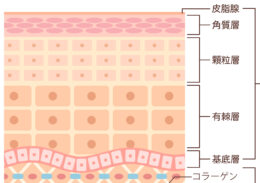札幌市を会場に8月5日から8日まで実施された東京五輪マラソン・競歩競技。男子マラソンで大迫傑選手が6位入賞、20Km競歩で池田向希選手が銀メダル、山西利和選手が銅メダルを獲得するなど、日本勢の活躍も目立ちました。茅ヶ崎市十間坂在住の常磐信欽さん(45)は、大会役員として運営を支えた1人。コロナ禍という特殊な状況のなか、間近で感じた「平和とスポーツの祭典」について聞きました。
「この数年、五輪のために多くの時間と労力を割いてきたので、今は終わってホッとした気持ち」と話す常磐さん。
競歩の審判員資格を持つ常磐さんのもとに、県陸上連盟から五輪への派遣要請があったのは5年ほど前といいます。2017年には国際陸連の審判員試験を受験。「問題も全て英語で本当に苦労しましたが、なんとか合格できました」
しかし準備段階では様々な要因に振り回されることに。酷暑への懸念から会場は札幌に変更、コロナ禍によって大会そのものが1年延期となりました。
ようやく迎えた大会期間中は、マラソンでは給水所の管理を、そして「本職」でもある競歩では国際審判であるポルトガル人のホセさんのアシスタントを務めました。
「過去にも国際大会で彼と組んだことがありました。温厚で周囲を気遣える人だったので真っ先に彼のところへ行って『一緒にやろう』と。彼も覚えてくれていました」。試合中はホセさんとともに、選手のフォームチェックや反則回数の集計などを担いました。
様々な制限のなか開催
コロナ禍のなかの開催で「バブル式」が徹底されたこともあり、ホテルではフロア間の移動も制限。目と鼻の先にある会場まで専用バスでの移動が義務付けられ「バスを何十分も待つこともあった」そうです。
それでも海外メディアの多さや外国語が飛び交う会場など、他の国際大会とは異なる「五輪ならではのステータス」を感じたそう。20Km競歩で日本勢を抑えて優勝したマッシモ・スタノ選手(イタリア)の歩行は「フォームも美しく、終盤になっても余裕があるように感じた」と大きな刺激を受けたといいます。
「経験を地域に還元したい」
常磐さんは茅ヶ崎市出身で梅田中学校時代に陸上を始めました。中距離の選手として活躍した後、高校の体育教諭に。鎌倉の女子校で陸上部の顧問をしていたとき「生徒の1人が競歩をやりたいと言い出して」経験ゼロから指導することになりました。
その後、試行錯誤の末に指導法を確立し、多くの教え子を全国大会に導いています。自身も審判員資格を取得し、競技環境の向上に取り組んできました。
現在は横浜市内の高校で陸上部の顧問を務める常磐さん。モットーは「自分で考える力を養うこと」といいます。
今回の経験を振り返り、「テレビで見た子どもたちが『競歩って面白そう』と始めるきっかけになったらうれしい。地元茅ヶ崎にも還元していけたら」と話していました。

現在は横浜市内の高校で陸上部顧問を務める常磐さん