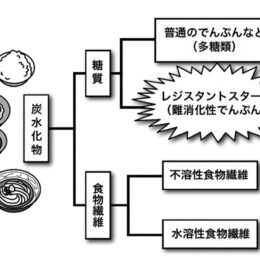7月21日(月・海の日)に開催される「浜降祭」。39基の神輿が茅ヶ崎西浜海岸に集結します。同じように見える神輿にも1基1基に違いや特徴が。ぜひ会場でチェックしてみてください!
萩園・三島大神

現在の神輿は1950年に二宮町の工房で作られたもの。それまで小ぶりの神輿で浜降祭に参加していた地域住民にとって待望の神輿だったそうです。胴の部分はケヤキの美しさを生かした白木づくりが特徴。正面の狛犬の彫刻には高度な透かし彫りの技法が使われています。神輿保存会顧問の青木春雄さん(88)は「祭りが始まるとつい体が動いてしまう」と話しています。
南湖・中町八雲神社

中町八雲神社の神輿は1888年に制作され、その後、寒川町の神社から譲り受けたと考えられています。四面の扉には牡丹や菊、長春花、蘭、欄間には飛龍や魚の彫刻が施され「立体的で細部にまで職人の技術が光る彫刻の見事さは随一」と評されているそう。4月に15年ぶりの修復を終え「地域のシンボルとして大切にしていきたい」と責任総代代表の尾高邦男さん(83)。神輿保存会には約120人が在籍し、浜降祭に向けて練習を重ねています。
本村八坂神社

本村八王子神社境内の八坂神社。今の神輿は「2代目」で1889年に作られたそうです。質の良いケヤキがふんだんに使われ約600kgと重いものの「その分しっかり作られている」といいます。金物には一般的な唐草ではなく菊があしらわれるなど装飾も特徴的。鳳凰が少し前傾しているのは「獲物を狙って飛び立つ瞬間と言われて格好いいんだ」と八王子神社総代の岸保二さん。
小和田熊野神社

小和田熊野神社の神輿は1978年に新調されました。大昔に他の神社との争いから神輿が海に流されてしまい、それ以来失ったままだったそうです。特徴は身長の高い鳳凰と、長い担ぎ棒。現在、神輿の生誕50周年を記念して修復を検討中だといい、白井幸雄さん(小和田熊野神社責任役員)は「皆さまのご協力をお願いいたします」と呼びかけています。
十間坂・第六天神社

1892年に愛川町半原の名工の手で完成。当時、地域の若者が漁師を手伝って費用を貯めた、という逸話が伝わっています。4本の柱は1本の木から掘り出され、それぞれに精巧な彫り物が施されている。屋根が少し小ぶりで「バランスが良く美しい」のが自慢。総代代表の大森健一さん(79)は「10歳から浜降祭に参加しているから、まだ70回しか出たことがない(笑)。やっぱり地域にとって大切なお祭り。ずっと守っていきたい」
南湖・上町金刀比羅神社

宮大工としても名を馳せた大山の名匠・89世手中明王太郎景元の手によって1877年に制作され、2回の修復を経て地域で支えてきました。前後の軒に優美な曲線が特徴の唐破風、左右の軒には直線的な千鳥破風が施されているのが特徴で「茅ヶ崎でもうちだけ」と松村邦夫総代表。「南湖はもともと漁師町でこの小さなまちから5社が浜降祭に参加していて南湖通りの盛り上がりは格別。浜降祭は1年に1度、情熱を燃やせる特別な日」と話しています。
円蔵・神明大神

神輿を待望する地域の声を受けて1880年に現在の二宮町山西の工房で製作されました。完成すると氏子たちが二宮から担ぎながら地域に戻ったという話が伝わっています。屋根を支える垂木の頭が龍になっているなど彫刻の見事さで知られるほか、茅ヶ崎市内で唯一、屋根に神紋がないのが特徴。総代長の野中誠さんは「神社が地域の交流拠点となり、普段からつながりが深いのが円蔵の特徴。祭りもしっかり受け継いでいきたい」
菱沼・菱沼八王子神社

菱沼八王子神社の神輿は明治初期、二宮の工房で完成したもの。「ゆったりと翼を広げた鳳凰の姿、垂木に彫刻された龍など装飾の素晴らしさはもちろん、屋根の反りが美しい。全体のバランスが良いので担ぎやすい」と役員の須田實さん。神輿とともに練り歩く神社旗は、祭りや神輿を愛する地元の人の団体「菱神会」が生地を京都から取り寄せるなどして奉納したものなのでぜひ注目を。
芹沢・腰掛神社

腰掛神社には1877(明治10)年に大山の棟梁が製作した神輿があったものの、1911(明治44)年に南湖の金刀比羅神社に譲渡。現在の神輿は1935(昭和10)年に新調されました。唐破風型の屋根が特徴で、屋根の真ん中にふくらみがあります。神輿保存会会長の太田三郎さんは「彫り物が『人の一生』のような物語になっているところに注目を」
西久保・日吉神社

日吉神社の神輿は1976年に氏子が寄付を募り製作しました。元々同社に神輿はなく、鶴嶺八幡社の神輿を担いでいたそうです。そのため、八幡社の神輿を模しているのが特徴で、勾欄(御堂の回廊の周りにある手摺り)の二重化や、シルエットなどが似ているとされています。責任役員代表総代を務める鈴木薫さんは「神事としての伝統を守っていきたい」と話しています。
矢畑・本社宮

本社宮の神輿は1978年に製作され、2007年に一度修復されました。茅ヶ崎市内最大級の鳳凰と上背が高いこと、胴体部分が素木づくりで十二支の彫刻が施されているのが特徴。浜降祭での神輿渡御は往路・復路とも自力渡御(一部で台車使用)を予定していて神輿世話人会会長の山上洋介さんは「矢畑の氏子皆で力を合わせて渡御したい」と話しています。
高田・高田熊野神社

真鍮鋳物でできた重量のある蕨手と台輪の四隅の波に千鳥の彫刻が特徴で、令和5年の修繕時に真鍮鋳物から欅に変更。昔、浜からも見えた高田の大松と八咫烏が前後に、左右には波に千鳥が刻まれている。台輪周りが欅の彫刻になっているのは高田だけ。浜のお立ちでは、松林地区九社で扇の形を作る。「見事な担ぎっぷりを見て欲しい」と浅岡肇総代。
中海岸・八大龍王神

八大龍王は古くから海の安全、豊漁、そして雨乞いの神様として日本各地で親しまれてきました。神輿は1978年にそのご神名をもって建立。2022年の修復を経て、建立から50周年を迎える28年には記念イベントが予定されています。神輿保存會の山神良友会長は「地域住民が協力して担ぎ練り歩くことで一体感を高める役割を果たします」と話しています。
中島・日枝神社

日枝神社の神輿は1872(明治5)年に製作され、最近では2014年に修復されています。神棚の階段がないため高過ぎず、担ぎ手たちにも「形やバランスが良い」と好評。手掘りの彫り物にもこだわりが。日枝神社神輿保存会会長の伊藤稔さんは「祭りでは担ぐ際に鈴がきれいに鳴るように難しい練習を積んできた。そこに注目してほしい」と話しています。
柳島・柳島八幡宮

神輿は空襲により焼失したが戦後に再建。9年前に大規模修復した。浜降祭で漁港の坂を下る様は鴇(とき)色の大群が押し寄せるかのように壮観。氏子のみで渡御しており、35歳の子供神輿役員から年を重ねるごとに様々な役を担い、48歳の年男が神輿渡御の責任者「丁頭(ちょうがしら)」を務めています。学年ごと、先輩後輩の協力体制も整っており、地域内の交流は深く、固い結束が自慢です。
浜之郷・鶴嶺八幡社

神輿は文化3(1806)年に製作され1995年に修復されたもの。二重勾欄と呼ばれる、勾欄が2段ある珍しい屋台形式は特徴の一つ。浜降祭のお発ちでは「先駆神社」としての役目を担い、鶴嶺八幡社4社が一斉に行う宮立(出発)に注目です。鶴嶺神輿愛好會会長の大川彰さんは「宮立ちから宮入まで担ぎっぱなしは鶴嶺だけ。そこも見てほしい」と呼びかけています。