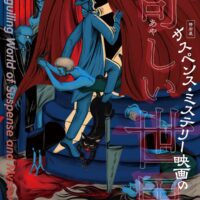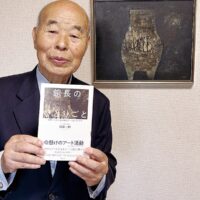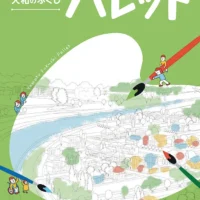小田原駅前の名産品販売店「小田原まると」(小田原市栄町)に4月下旬、東京都の明治大学博物館から問い合わせがあった。同館が所蔵している「小田原人形」について何か情報を知らないか、という内容だった。
「小田原人形」は、胡粉や布地で作られている人形。「小田原かまぼこ」と書かれた法被を着て、右肩に巨大なかまぼこを担ぎ、左手に小田原ちょうちんを下げているのが特徴。大きさは、高さ14・3センチ、幅8センチ。同館が地方の物産品収集を目的に、1963年に同店で木工品などとともに購入したと資料台帳に記されているが、それ以外の情報はほとんど不明だという。
問い合わせを受けた同店の穂坂肇社長(63)は、メールで送られた写真を見たが、「見覚えがなかった」という。同館の資料台帳によると、人形の購入金額が200円。60年代の初任給が約1万円だったことから、穂坂社長は「当時では高価な土産物だったのでは」と話す。
同館は収蔵品をデジタルデータとして保存しており、今回は50〜60年代に特有の商品を調査。小田原人形はその一環で情報収集が行われていた。同館によると60年代の日本各地では、郷土の習俗をモチーフにした人形が土産物として製造されており、同様の人形が他にも確認されているという。担当者は「特定の人形製造の会社が各地に卸していた可能性もあるのでは」と推察している。
「有力な手がかりない」
穂坂社長は自ら、市内の木工関係者やかまぼこ生産者などに話を聞いたほか、SNSで情報提供を呼び掛けたが「いまだに有力な手がかりは得られていない」と話す。
本紙も市郷土文化館の担当者に話を聞いたが、関連する記録は確認できていないという。
調査にあたり同館は、製造業者や生産場所、作成経緯などの情報提供を広く募っている。また、「地元小田原でこの人形の存在を知ってほしい」と、思いを語った。
問い合わせは、明治大学博物館【電話】03・3296・4448(午前10時〜午後5時、土曜日は4時まで、日曜・祝日休館)。