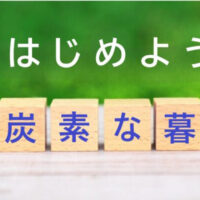茅ヶ崎公園体験学習センター「うみかぜテラス」が主催する第9回環境学び講座「姥島(烏帽子岩)自然観察会」が5月25日に開催されました。「#ちがすき」記者も同行してきましたので、当日の様子をレポートします。
朝、26人の参加者が茅ヶ崎漁港に集合。イベントに協力してくれている釣り船「えぼし丸」で港からわずか10分足らず。目的の烏帽子岩に到着しました。
足元に気を配りながら上陸すると目の前にあの見慣れた岩が!(諸説あるものの高さは15メートルほどだそう)。参加者のほとんどがもちろん初上陸で「これが実物か」と感激もひとしおの様子です。

ついに上陸!
地層が語る烏帽子岩の誕生から現在
そしてこの観察会には、地質と生き物の専門家3人が同行しており、それぞれの分野から烏帽子岩を深堀りしました。
布施憲太郎さん(三浦半島活断層調査会)は地質の専門家。烏帽子岩は黒い層(スコリア)と白い層(パミス)という、いずれも火山からの噴出物が交互に重なってできている、と布施さん。約1200万年前、数百キロも南の海底で誕生した海底火山がプレートに乗って移動し、現在の場所までやってきたのが烏帽子岩だと語ります。

地質の観点から烏帽子岩の成り立ちについて語る布施さんの解説に参加者は興味津々
岩に見える地層が水平でなく斜めに見えるのは「今もプレートに押され続けてだんだん傾いているため」とのこと。地層が語りかけるダイナミックな地球の営みに、参加者の皆さんも驚きの声を上げます。
烏帽子岩では初?のアメフラシを発見
続いて生物の専門家、岸一弘さん(日本生態学会、日本トンボ学会、茅ヶ崎野外自然史博物館)が登場。この時期の烏帽子岩は、キョウジョシギなど渡り鳥たちの休息場所となっているそうですが、残念ながらこの日は姿が見えず。ただ代わりに大きな発見がありました。

潮溜まりをのぞきこむ参加者の皆さん
烏帽子岩の生き物を特徴づけている潮溜まり(タイドプール)で、体長が50㎝はあるアメフラシが発見されたのです。長年、烏帽子岩の生物を見てきた岸さんも「こんな大物が観察されたのは烏帽子岩では初めてのはず。県内でも観察例はほとんどないのでは」と興奮を隠せません(のちにショウワアメフラシという普段はもっと南に生息している判明したそうです)。
- 潮溜まりで発見されたショウワアメフラシ
- 防水仕様のカメラで撮影したアメフラシ(参加者の程島恭一さん提供)
- 模様が美しい!(程島恭一さん提供)
特設「えぼし水族館」が登場
最後に「お魚コミィ」として磯遊びの楽しさなどを発信している海辺の生き物の専門家、小峯和朗さんは潮溜まりなどにいる魚や甲殻類などをその場で小さな水槽に入れ、即席の水族館を作ってくれました。

即席の水族館を作った小峯さん
背中のトゲには毒があるものの、姿はかわいい「ハオコゼ」、江戸時代の駕籠を語源とする「カゴカキダイ」の稚魚、頭に海藻をつけて身を隠す「ヨツハモガニ」、名前から美しい「アヤニシキ(綾錦)」と呼ばれる海藻など、小さな潮溜まりに多種多様な生き物たちがいることに参加者たちも感心しきり。小峯さんも「いまの季節らしいたくさんの生き物との出会いに恵まれていい観察会になりました」と話していました。
- 潮溜まりには様々な生き物たちが(写真はいずれも小峯さん提供)
こうして約2時間の充実した観察会はあっという間に終了。参加者の皆さんは
「浜辺から眺めることしかできなかった烏帽子岩に初めて上陸できて感激しました。どのような成り立ちで烏帽子岩ができたのか、またさまざまな生命の営みがあると知りさらに勉強になりました」(程島恭一さん・58)
「普段は岩の部分しか見えませんが、上陸してみて島としても相当な広さがあることが分かりました。専門家の方たちの話は門外漢の自分が聞いても興味深く、とても楽しかった」(谷口裕信さん・67)
「解説を聞くことでさらに深く知ることができました。こんなに生き物がいるとは思わなかったし、烏帽子岩そのものも生きているように感じました。今日聞いたことを知人や友人にも伝えたい」(桑原恵美子さん・48)
などと感想を話していました。